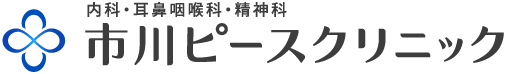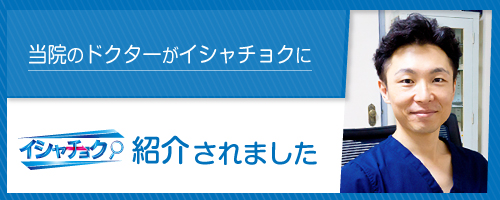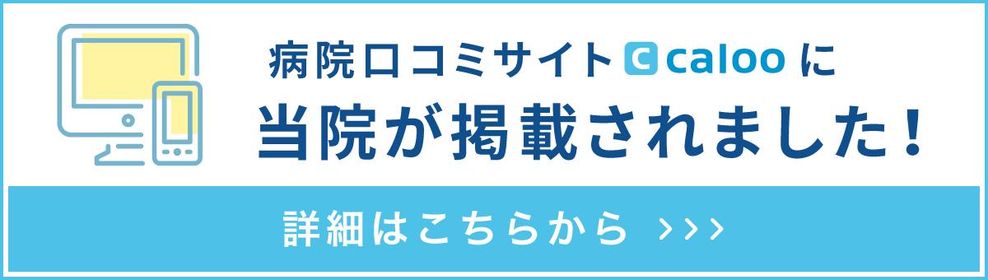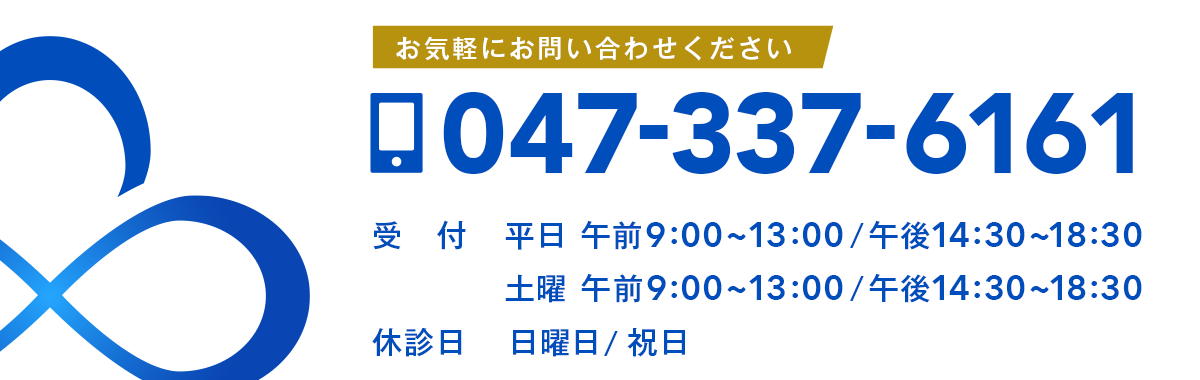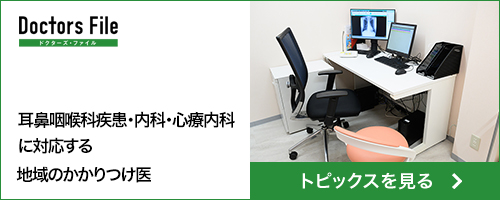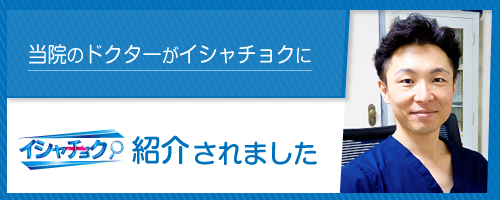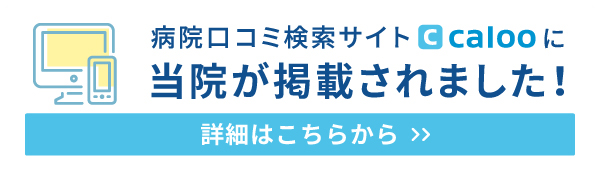あなたの血管は大丈夫?動脈硬化リスクを測る検査
あなたは、いつまでも健康でいたいと願っていますか?しかし、目に見えない体の変化が、将来の健康を脅かしているかもしれません。
それは、動脈硬化です。
気づかないうちに進行し、心筋梗塞や脳梗塞といった命に関わる病気を引き起こす可能性のある、恐ろしい病気です。 40歳以上では、自覚症状がないまま進行しているケースも少なくありません。
この記事では、動脈硬化の基礎知識から、早期発見に繋がるCAVI、ABI、眼底検査といった具体的な検査方法まで、分かりやすく解説します。 あなたの血管年齢はいくつ? 静かに忍び寄る動脈硬化の脅威から身を守るために、今すぐ知っておくべき情報が満載です。 検査の種類、流れ、そして異常値が出た場合の対処法まで、詳しくご紹介します。 健康な未来のために、この機会にあなたの血管と向き合ってみませんか?
動脈硬化の基礎知識:定義とメカニズム

血管は、体中に酸素や栄養を運ぶための重要なライフラインです。しかし、このライフラインである血管も、加齢とともに老化していくことをご存知でしょうか?その老化現象の一つが、動脈硬化です。動脈硬化は誰にでも起こりうる変化ですが、放置すると様々な病気を引き起こす可能性があります。今回は、動脈硬化の仕組みや合併症について、わかりやすく解説します。
動脈硬化とは何か
動脈硬化とは、血管の壁が硬く、厚く、そしてもろくなってしまう病気です。血管の壁は、内膜、中膜、外膜の3層構造になっており、健康な血管は内膜がなめらかで弾力性があり、血液がスムーズに流れます。例えるなら、新品のゴムホースのようなしなやかさを持っているのです。
しかし、動脈硬化になると、血管の内膜にコレステロールなどの脂肪が溜まり、血管の内側が狭くなります。これは、ゴムホースの内側に油汚れがこびりついて、ホースの内径が狭くなるようなイメージです。さらに、血管の壁は厚く硬くなり、弾力性を失ってしまいます。まるで、ゴムホースが古くなって硬くなり、曲げにくくなるような状態です。
動脈硬化は、自覚症状がないまま徐々に進行することが多く、気づかないうちに病気が進行しているケースも少なくありません。静かに進行する恐ろしい病気と言えるでしょう。
動脈硬化の進行メカニズム
動脈硬化は、血管の内膜にコレステロールが溜まることから始まります。高血圧、糖尿病、喫煙、脂質異常症などの危険因子が重なると、血管の内膜は傷つきやすくなります。傷ついた内膜にコレステロールなどの脂肪が付着し、血管の壁が炎症を起こし、血管が硬く厚くなっていきます。
この状態が続くと、血管の内側が狭くなり、血液の流れが悪くなります。血液の流れが悪くなると、酸素や栄養が体の隅々まで届かなくなり、様々な臓器に悪影響を及ぼします。水道管が詰まって水が流れにくくなるのと同じように、血管が詰まると体の各部に必要な血液が供給されにくくなるのです。
納豆キナーゼのように抗血栓作用や血圧低下作用が期待される成分もありますが、健康な人においては、動脈硬化の進行抑制に効果がないという研究結果も出ています。動脈硬化の予防・改善には、危険因子をコントロールすることが非常に重要です。
高血圧であれば塩分を控える、糖尿病であればバランスの良い食事を摂る、喫煙であれば禁煙する、脂質異常症であれば動物性脂肪を控えるなど、生活習慣の改善が不可欠です。
動脈硬化が引き起こす合併症
動脈硬化が進行すると、血管が詰まったり破れたりして、様々な病気を引き起こします。代表的な合併症には、心筋梗塞、脳梗塞、狭心症などがあり、命に関わる危険な病気も含まれます。
心筋梗塞は、心臓の血管が詰まり、心臓の筋肉に血液が供給されなくなる病気です。激しい胸の痛みや呼吸困難などの症状が現れ、突然死につながることもあります。脳梗塞は、脳の血管が詰まり、脳の細胞に血液が供給されなくなる病気です。手足の麻痺やしびれ、言語障害などの症状が現れ、後遺症が残ることもあります。狭心症は、心臓の血管が狭くなり、心臓に十分な血液が供給されなくなる病気で、胸の痛みや圧迫感などの症状が現れます。
ビスホスホネートという薬は、骨粗鬆症などの治療薬として知られていますが、研究によると動脈壁へのコレステロールの蓄積を抑制する効果や、血管の炎症を抑える効果など、様々なメカニズムで動脈硬化の進行を抑制すると考えられており、動脈硬化の予防にも効果があることが示唆されています。
動脈硬化は、心臓や脳だけでなく、腎臓や足などの血管でも起こる可能性があります。全身の血管で起こる病気であることを理解しておくことが重要です。動脈硬化を予防するためには、危険因子をコントロールすることが大切です。バランスの取れた食事、適度な運動、禁煙などを心がけ、健康な血管を維持しましょう。
動脈硬化を測る検査方法:CAVI、ABI、眼底検査の違い

動脈硬化は、自覚症状がないまま進行し、気づいたときには重症化しているケースも少なくありません。そのため、定期的な検査で早期発見・早期治療につなげることが非常に重要です。動脈硬化の検査にはいくつかの種類があり、それぞれ検査対象となる血管や測定方法が異なります。今回は代表的な検査方法として、CAVI、ABI、眼底検査について詳しく解説します。これらの検査は、痛みを伴わず、短時間で簡単に血管の状態を調べることができますので、ご安心ください。
CAVI検査の概要とメリット
CAVI(Cardio-Ankle Vascular Index:心臓足首血管指数)検査は、心臓から足首までの動脈の硬さを数値化して評価する検査です。この検査の最大の特徴は、血圧の影響を受けにくい点にあります。血圧は時間帯や体調によって変動するため、動脈硬化の程度を正確に測るには、血圧の影響を除外することが重要です。CAVI検査は、心電図と脈波を同時に記録することで、血圧に左右されずに動脈の硬さを評価することができるのです。
検査方法は、両腕と両足首にカフ(血圧計で使う帯のようなもの)を巻いて、安静にした状態で数分間計測するだけです。痛みは全くありません。検査結果はCAVI値として表され、この数値が高いほど動脈硬化が進んでいることを示します。CAVI値から血管年齢を推定することも可能です。
CAVI検査は、動脈硬化の早期発見に非常に役立ちます。動脈硬化は初期段階では自覚症状がほとんどないため、定期的なCAVI検査で血管の状態を客観的に評価することは、将来的な血管疾患のリスク管理に不可欠と言えるでしょう。
ABI検査の基礎知識とその重要性
ABI(Ankle-Brachial pressure Index:足関節上腕血圧比)検査は、足首と上腕の血圧の比を測定することで、足の血管の詰まり具合を評価する検査です。ABI検査は、費用が比較的安く、簡便に実施できるため、動脈硬化のスクリーニング検査として広く用いられています。
検査方法は、両腕と両足首の血圧を測定し、足首の血圧を上腕の血圧で割った値をABI値として算出します。健康な人のABI値は1.0~1.4です。ABI値が1.0未満の場合は、足の血管が狭くなっていたり、詰まっていたりする可能性が高いことを示唆しています。特に0.9以下の場合は、末梢動脈疾患(PAD)が疑われます。PADは、足の血管が動脈硬化によって狭窄または閉塞し、足の血流が悪くなる病気です。初期には自覚症状がない場合もありますが、進行すると歩行時に痛みやしびれが生じ、さらに重症化すると安静時にも痛みが出現したり、潰瘍や壊疽(組織の壊死)を引き起こすこともあります。
ABI検査は、PADの早期発見・早期治療に非常に重要です。PADは適切な治療を行えば進行を遅らせたり、症状を改善したりすることが可能です。ABI検査で異常値が検出された場合は、速やかに専門医を受診し、適切な治療を受けるようにしましょう。
眼底検査で分かる動脈硬化の兆候
眼底検査は、眼の奥にある網膜の血管を観察する検査です。網膜の血管は、体の中で唯一直接観察できる血管であるため、眼底検査を行うことで全身の動脈硬化の兆候を捉えることができます。高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病も、眼底検査で確認できることがあります。
検査方法は、散瞳薬(瞳孔を開く目薬)を使用して瞳孔を拡大し、眼底カメラで網膜の血管を撮影します。検査時間は数分程度で、痛みもありません。眼底検査では、動脈硬化によって引き起こされる血管の変化(血管の狭窄、硬化、出血など)を直接観察することができます。これらの変化は、全身の動脈硬化の進行度合いを反映している可能性があります。
例えば、動脈が細くなっていたり、硬くなっていたり、出血していたりする場合は、動脈硬化が進行している可能性が高いと考えられます。また、眼底検査で動脈硬化の兆候が見つかった場合、全身の他の部位でも動脈硬化が進行している可能性が高いため、注意が必要です。
納豆キナーゼのような健康食品の摂取が、心血管疾患リスクの低い健康な人の動脈硬化の進行抑制に効果がないという研究結果も出ています。動脈硬化の予防には、バランスの取れた食事、適度な運動、禁煙など、日々の生活習慣の見直しが非常に重要です。眼底検査は、全身の血管の状態を把握する上で重要な検査ですので、定期的に受診することをお勧めします。
動脈硬化検査の流れと受診のポイント

血管の健康状態を把握することは、全身の健康維持に不可欠です。動脈硬化は自覚症状に乏しいまま進行し、心筋梗塞や脳梗塞といった生命に関わる病気を引き起こす危険性があります。
ご自身の血管の状態を正しく理解し、適切な対策を講じるために、動脈硬化の検査について理解を深めていきましょう。今回は、代表的な検査であるCAVI、ABI、眼底検査について、その流れと受診のポイントを詳しく解説します。これらの検査は、痛みを伴わず比較的短時間で完了するため、身体への負担も少なく受診しやすいというメリットがあります。
まず、動脈硬化検査は、大きく分けて以下の3つのステップで進みます。
-
問診・診察:
現在の症状や既往歴、生活習慣、服薬状況などを医師が詳しく確認します。ご自身の健康状態や生活習慣について正確に伝えることが、適切な検査と診断につながるため、些細なことでも医師に相談することが大切です。
-
検査の実施:
CAVI、ABI、眼底検査など、医師が必要と判断した検査を行います。検査の種類によっては、事前の食事制限や服薬に関する指示がある場合もありますので、事前に医療機関の指示をよく確認しておきましょう。それぞれの検査について簡単に説明すると、CAVIは心臓から足首までの動脈の硬さを、ABIは足首と上腕の血圧比を測定することで足の血管の詰まり具合を、眼底検査は網膜の血管を観察することで全身の動脈硬化の兆候を評価します。
-
結果説明と今後の対応:
検査結果に基づいて、医師が現在の血管の状態や今後のリスクについて丁寧に説明します。結果によっては、生活習慣の改善指導や治療が必要となる場合もあります。動脈硬化の治療は、食事療法、運動療法、薬物療法など多岐にわたるため、医師とよく相談し、ご自身に合った治療法を選択していくことが重要です。
検査を受けるべき年齢と頻度
動脈硬化は加齢とともに進行しやすいため、年齢を重ねるごとに検査の重要性が増していきます。特に40歳以上の方は、自覚症状がなくても動脈硬化が進行している可能性があるため、定期的な検査が推奨されます。
40歳未満の方でも、高血圧、糖尿病、脂質異常症、喫煙、肥満、家族歴などの危険因子がある場合は、若年期から動脈硬化のリスクが高まるため、医師の判断に基づき定期的な検査を受ける必要があります。
また、健康食品やサプリメントを摂取しているからといって安心はできません。例えば、納豆キナーゼは抗血栓作用や血圧低下作用があるとされていますが、心血管疾患リスクの低い健康な人の動脈硬化の進行抑制には効果がないという研究結果も報告されています。大切なのは、日々の生活習慣の見直しと定期的な検査による客観的な評価です。
検査頻度は、個々のリスクや健康状態によって異なりますが、一般的には以下の目安を参考にしてください。
-
40歳未満:
健康診断時または医師の指示に従う
-
40歳以上:
年に1回
-
動脈硬化の危険因子を持つ方:
医師の指示に従う
ご自身の状況に不安がある場合は、医師に相談し、適切な検査頻度を決定しましょう。
検査予約の方法と流れ
検査の予約方法は、医療機関によって異なりますが、多くの場合、電話やインターネットで予約が可能です。予約時に、検査内容や費用、必要な持ち物などを確認しておくとスムーズです。
検査当日の流れは、以下のとおりです。
-
受付・問診票記入:
医療機関に到着したら、受付を済ませ、問診票に必要事項を記入します。
-
血圧測定・採血:
血圧を測定し、必要に応じて血液検査を行います。
-
CAVI、ABI、眼底検査:
それぞれの検査について、医師または検査技師から説明を受けながら検査を進めます。
-
結果説明:
検査終了後、医師から結果の説明と今後の対応について説明を受けます。
検査結果が異常だった場合の対処法
検査結果が異常値を示した場合、動脈硬化の進行度合いによって、生活習慣の改善指導や薬物療法などの治療が必要になります。
生活習慣の改善としては、バランスの取れた食事、適度な運動、禁煙などが重要です。特に食事においては、コレステロールや飽和脂肪酸の摂取を控え、野菜や果物を積極的に摂ることを心がけましょう。運動は、ウォーキングなどの有酸素運動を継続して行うことが効果的です。
薬物療法では、動脈硬化の進行を抑える薬や、合併症を予防するための薬が処方されることがあります。例えば、ビスホスホネート系薬剤は、骨粗鬆症の治療薬として知られていますが、動脈壁へのコレステロールの蓄積を抑制する効果や血管の炎症を抑える効果などが報告されており、動脈硬化の予防にも効果があることが示唆されています.
動脈硬化は放置すると、心筋梗塞や脳梗塞などの重篤な合併症を引き起こすリスクが高まります。検査結果が異常だった場合は、医師の指示に従い、適切な治療と生活習慣の改善に取り組むことが大切です。
まとめ
あなたの血管年齢、知っていますか?動脈硬化は自覚症状がないまま進行し、気づいたときには手遅れということも。CAVI、ABI、眼底検査といった検査で、あなたの血管の状態を客観的に知ることができます。40歳以上の方や、高血圧、糖尿病などリスクのある方は、ぜひ一度検査を受けてみましょう。早期発見・早期治療が、健康な生活を送るための近道です。検査は痛みも少なく、短時間で済みます。まずはかかりつけ医に相談し、あなたに合った検査方法を選び、血管の健康を守りましょう。 心配な方は、今日からでも野菜中心の食事や適度な運動を心がけて、健康的な生活習慣を送り始めることをおすすめします。小さな習慣が、未来の健康を大きく左右します。
参考文献
1.Hodis HN, Mack WJ, Meiselman HJ, Kalra V, Liebman H, Hwang-Levine J, Dustin L, Kono N, Mert M, Wenby RB, Huesca E, Rochanda L, Li Y, Yan M, St John JA and Whitfield L. “Nattokinase atherothrombotic prevention study: A randomized controlled trial.” Clinical hemorheology and microcirculation 78, no. 4 (2021): 339-353.
2.Ylitalo R. “Bisphosphonates and atherosclerosis.” General pharmacology 35, no. 6 (2000): 287-96.