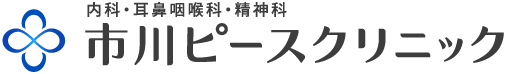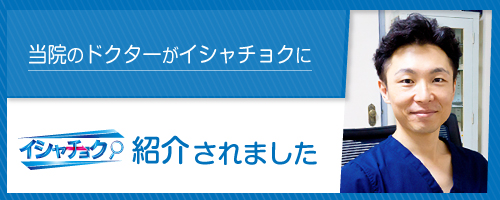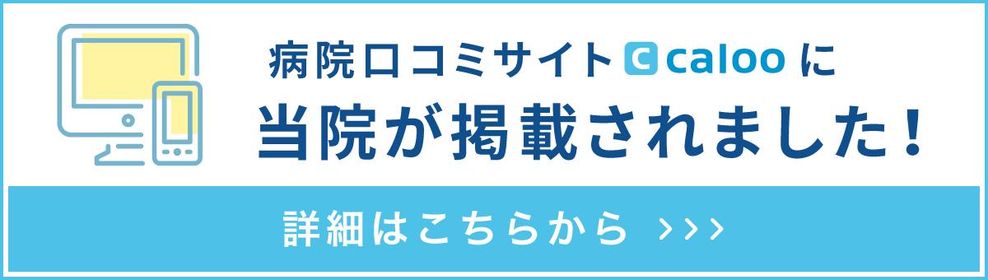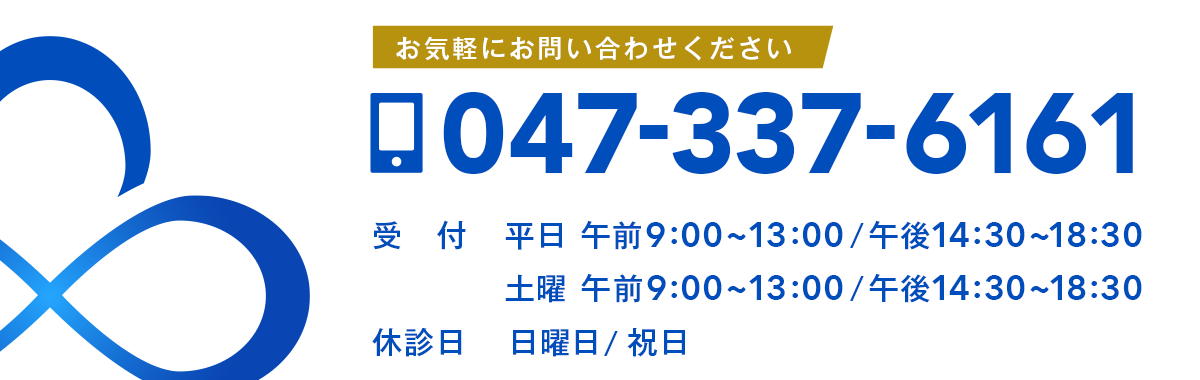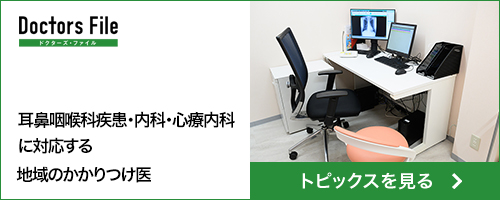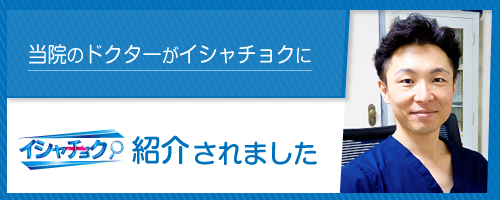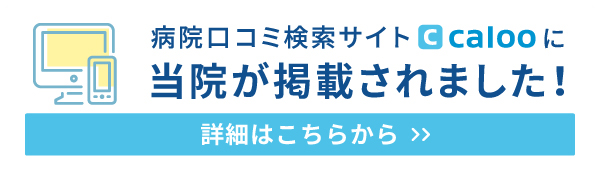心電図で引っかかったら?受診前に知っておきたいこと
健康診断で「心電図異常」の文字を見た時、あなたはどんな気持ちでしたか?心臓に何か重大な問題があるのでは…と不安になったのではないでしょうか。実は、心電図異常は必ずしも深刻な病気とは限りません。しかし、中には放置すると危険な状態に繋がるものも存在するのです。
2023年現在、日本人の死因の上位を占める病気の多くは心臓血管疾患に関連しています。心電図異常は、これらの病気の早期発見に繋がる重要なサインかもしれません。この記事では、代表的な心電図異常である短QT症候群や肥大型心筋症の特徴、症状、そして治療法について詳しく解説します。
さらに、心電図異常による様々な心拍の変化や、疲労感・息切れといった自覚症状についても具体的に説明します。健康診断で異常を指摘された方、あるいは日頃から胸の痛みや動悸を感じている方は、ぜひこの記事を読んで、自身の状態と照らし合わせてみてください。
もしかしたら、あなたを救う重要な情報が隠されているかもしれません。早期発見・早期治療こそが、健康な未来を守る鍵となります。
心電図異常の種類と特徴を知ろう

健康診断などで「心電図異常」と告げられたら、不安になりますよね。心臓に何か問題があるのかと心配になるのも当然です。心電図は心臓の電気的な活動を記録したもので、この波形が通常と異なるパターンを示すと「心電図異常」と診断されます。
実は、心電図異常には様々な種類があり、必ずしも深刻な病気を意味するとは限りません。しかし、中には注意が必要な異常もありますので、種類と特徴を正しく理解することが大切です。この記事では、代表的な心電図異常をいくつかご紹介します。
短QT症候群とその影響
短QT症候群(SQTS)は、心臓の電気信号の伝わり方に異常が生じる病気です。心電図を見ると、QT間隔と呼ばれる部分が通常よりも短くなっています。このQT間隔は、心臓が収縮し再び拡張するまでの時間を表しています。
QT間隔が短いということは、心臓の収縮と拡張のリズムが速くなっていることを意味します。1999年に発見された比較的新しい疾患で、遺伝子の変化が原因となることが多いです。短QT症候群は、心房細動などの不整脈や、最悪の場合、突然死を引き起こすリスクがあります。
心電図検査でこの病気を発見することは容易ではありません。特に、お子さんの場合は見落とされる可能性も高いです。なぜなら、QT間隔の短縮は、心拍数が1分間に80回以下の時に初めてはっきり認識できるからです。また、健康な人でも、まれに短QT間隔を示す場合があり、専門医による詳細な評価が必要です。
現在、決定的な治療法は確立されていませんが、抗不整脈薬であるプロパフェノンを用いて心房細動の発生を抑制したり、植込み型除細動器(ICD)を体内に埋め込んで突然死のリスクを低減する治療が行われています。ICDは、心臓の危険な不整脈を感知し、電気ショックを与えて正常なリズムに戻す働きをする機器です。
肥大型心筋症の症状と治療
肥大型心筋症は、心臓の筋肉、特に左心室の壁が厚くなってしまう病気です。遺伝的要因が関わっている場合が多く、心電図にも異常が現れることがあります。心臓の壁が厚くなると、心臓内に血液がスムーズに流れにくくなり、様々な症状が現れます。
代表的な症状は、動悸、息切れ、めまい、失神などです。また、胸の痛みを感じる方もいます。肥大型心筋症は、突然死のリスクを高める可能性もあるため、注意が必要です。症状の程度は個人差が大きく、無症状の方もいれば、重度の心不全症状を呈する方もいます。
治療法は、薬物療法と手術があります。薬物療法では、β遮断薬やカルシウム拮抗薬を用いて心臓の負担を軽減します。β遮断薬は心拍数を抑え、心臓の収縮力を弱めることで心臓の負担を軽減します。カルシウム拮抗薬は、心臓の筋肉の収縮を抑制し、血管を拡張することで心臓の負担を軽減する効果があります。症状が重い場合や薬物療法で効果が不十分な場合は、手術を行うこともあります。肥大型心筋症は進行性の病気であるため、定期的な検査と適切な治療を継続することが非常に重要です。
日常生活では、激しい運動を避け、バランスの取れた食事と十分な睡眠を心がけるなど、健康的な生活習慣を維持することが大切です。
その他の心電図異常の具体例
心電図異常には、短QT症候群や肥大型心筋症以外にも様々な種類があります。それぞれ原因や症状、治療法が異なります。代表的なものとして、WPW症候群、ブルガダ症候群、QT延長症候群などがあります。
WPW症候群は、心臓内に余分な電気の通り道(副伝導路)があることが原因で、動悸やめまいなどの症状が現れます。カテーテルアブレーションという治療法で、この余分な通り道を焼灼することで症状を改善できる場合があります。
ブルガダ症候群は、特定の遺伝子異常が原因で、意識消失や突然死のリスクがあります。植込み型除細動器(ICD)を埋め込むことで、突然死を予防できる場合があります。
QT延長症候群は、QT間隔が異常に長いことが特徴で、ふらつきや失神、不整脈などの症状が現れます。薬物療法やICDの埋め込みなどが行われます。
心電図で異常が見つかった場合は、必ず医療機関を受診し、専門医の診察を受けるようにしましょう。自己判断は危険です。医師の指示に従って適切な検査や治療を受けることが大切です。
心電図異常の自覚症状と検査方法

健康診断で「心電図に異常があります」と言われても、具体的に何がどう異常なのか、すぐに理解するのは難しいですよね。実際、私も医師として多くの心電図を見てきましたが、波形だけを見てもすぐには判断できない複雑なケースも少なくありません。だからこそ、患者さん自身も心電図検査で何がわかるのか、どのような症状に注意すべきかを理解しておくことが大切です。
心電図異常による心拍の変化
心電図は、心臓の電気的な活動を波形として記録したものです。この波形を丁寧に読み解くことで、心臓が規則正しく活動しているか、脈が速すぎたり遅すぎたりしていないか、心臓の筋肉に十分な酸素が供給されているかなど、様々な情報を得ることができます。
心電図異常で多く見られるのは、脈のリズムが乱れる「不整脈」です。脈が異常に速くなる「頻脈」、逆に遅くなる「徐脈」、脈が飛ぶように感じる「期外収縮」など、様々な種類があります。これらの不整脈は、自覚症状が全くない場合もあれば、動悸やめまい、さらには失神といった深刻な症状を引き起こす場合もあります。
また、心電図では、心臓の筋肉への酸素供給が不足している状態(狭心症や心筋梗塞)を示す異常も検出できます。これは、心電図の波形の一部であるST部分の変化から判断します。健康な方であればST部分は比較的平坦な形状をしていますが、酸素不足の状態になるとこの部分が上昇したり下降したりといった変化が現れるのです。
疲労感や息切れを伴う自覚症状
心電図異常は、必ずしも自覚症状を伴うとは限りません。健康診断で偶然発見されるケースも珍しくありません。しかし、自覚症状が現れる場合、その症状は心電図異常の種類によって大きく異なります。
例えば、脈が速くなる頻脈の場合、動悸やめまい、息切れといった症状が現れることがあります。脈拍が1分間に100回を超えると、安静時でもドキドキとした動悸を自覚する方が多いです。また、脈が遅くなる徐脈では、倦怠感、ふらつき、失神などの症状が現れることがあります。健康な方の脈拍は通常1分間に60~100回程度ですが、徐脈ではこれが50回以下になることもあり、脳への血流が不足しやすくなります。期外収縮では、脈が飛ぶような感覚や胸の違和感を感じる方もいます。これは、心臓が本来のリズムとは異なるタイミングで収縮することで生じる症状です。
狭心症や心筋梗塞といった心臓の酸素不足を示す心電図異常の場合、胸の痛みや圧迫感、息苦しさ、吐き気などの症状が現れることがあります。狭心症では、運動時やストレスを感じた時などに胸の痛みが数分間続くことが多い一方、心筋梗塞ではより強い痛みが持続し、冷や汗や吐き気などを伴うこともあります。これらの自覚症状は他の病気でも起こりうるため、心電図異常との関連を正確に判断するには、医療機関を受診し医師の診察と検査を受けることが重要です。
検査方法と精密検査の流れ
心電図検査は、体に電極を貼り付けて心臓の電気的活動を記録する簡便で痛みを伴わない検査です。健康診断で行われるのは、安静時の心電図検査です。しかし、安静時には異常がなくても、運動中などに異常が現れる場合もあります。そこで、運動負荷心電図検査を行うこともあります。これは、トレッドミル(ランニングマシン)の上を歩きながら、あるいは自転車型のエルゴメーターを漕ぎながら心電図を記録する検査で、運動時の心臓の状態を評価できます。
さらに詳しい検査が必要な場合は、24時間心電図(ホルター心電図)検査を行います。小型の記録装置を装着し、日常生活を送りながら24時間心電図を記録することで、安静時には見つからない異常を発見できる可能性が高まります。日常生活での活動中の心臓の状態を長時間モニタリングできるため、期外収縮などの頻度や時間帯による変化を把握するのに役立ちます。
また、心臓超音波検査(心エコー)も重要な検査です。これは、超音波を使って心臓の動きや構造をリアルタイムで観察する検査です。心臓の弁の状態や心筋の厚さ、心臓のポンプ機能などを評価することができます。心エコー検査では、心臓の各部屋の大きさや壁の厚さ、弁の開閉の様子などを動画で確認できるため、形態的な異常や機能的な異常を詳細に評価することができます。
これらの検査結果に基づいて、必要に応じて心臓カテーテル検査などのより専門的な検査を行い、診断を確定していきます。短QT症候群のように、心電図でQT間隔の短縮が見られる場合は、特に安静時の心拍数が低い時に初めて明らかになるため注意が必要です。心拍数が低い状態では心電図の波形が短縮され、異常が見落とされやすいため、安静時だけでなく運動負荷心電図検査など、複数の検査を組み合わせて総合的に判断することが重要です。
心電図異常に対する治療法と生活習慣

健康診断で心電図異常を指摘された時、どんな治療が必要なのか、生活はどう変わるのか、不安でいっぱいになる方もいるでしょう。実際に私も外来で、心電図の結果を聞いた途端、青ざめてしまう患者さんを何人も見てきました。
心電図異常は、心臓の電気信号の伝わり方に乱れが生じている状態です。しかし、その原因や重症度は実に様々です。軽度の異常であれば、経過観察だけで済む場合もありますし、重度の異常であれば、早急な治療が必要となる場合もあります。
大切なのは、ご自身の心電図異常がどのような種類で、どのような治療が必要なのかを正しく理解することです。この章では、心電図異常に対する様々な治療法と、日常生活で気を付けるべき点について、具体的に解説していきます。
医療機関での治療法とその効果
心電図異常の治療は、異常の種類や程度、そして患者さんの年齢や全身状態を総合的に判断して決定されます。主な治療法としては、薬物療法、カテーテルアブレーション、ペースメーカー植え込み術、植込み型除細動器(ICD)植え込み術などがあります。
薬物療法は、不整脈の発生を抑えたり、心臓の負担を軽減したりする薬を服用します。例えば、脈が速すぎる場合は、心拍数を抑える薬を使用します。脈が遅すぎる場合は、心拍数を上げる薬を使用します。また、心臓の筋肉の収縮力を強める薬や、心臓の血管を広げる薬なども用いられます。これらの薬は、心電図異常の症状を改善し、心臓の機能を維持するのに役立ちます。ただし、薬には副作用がある場合もあるため、医師の指示に従って正しく服用することが大切です。
カテーテルアブレーションは、心臓内に細い管(カテーテル)を挿入し、不整脈の原因となっている異常な電気信号を発する部分を高周波電流で焼灼する治療法です。この治療法は、一部の不整脈に対して非常に有効で、薬物療法で効果が不十分な場合や、薬の副作用が強い場合に検討されます。
ペースメーカー植え込み術は、心臓の拍動が遅すぎる場合に、適切なリズムで電気刺激を与えて心臓の働きを助ける治療法です。小型のペースメーカーを皮下に埋め込み、そこからリードと呼ばれる細い電線を心臓内に挿入します。ペースメーカーは、心臓の拍動が遅くなった時に自動的に電気刺激を送るため、めまいや失神などの症状を予防することができます。
植込み型除細動器(ICD)植え込み術は、心停止につながるような危険な不整脈が発生した場合に、電気ショックを与えて心臓のリズムを正常に戻す治療法です。ICDもペースメーカーと同様に皮下に埋め込まれ、心臓内にリードが挿入されます。ICDは、危険な不整脈を感知すると自動的に電気ショックを与え、心臓の動きを正常な状態に戻します。突然死の予防に効果的な治療法です。
1999年に発見された短QT症候群(SQTS)は、心電図でQT間隔の短縮が見られる遺伝性の病気です。この病気は、心房細動や突然死のリスクを高めることが知られています。治療法としては、抗不整脈薬であるプロパフェノンを用いて心房細動の発生を抑制する方法や、ICDを埋め込んで突然死を予防する方法があります。
生活習慣の改善がもたらす影響
心電図異常の治療や予防には、医療機関での治療だけでなく、日常生活における生活習慣の改善も非常に重要です。健康的な生活習慣を維持することで、心臓の負担を軽減し、心電図異常の悪化や再発を予防することに繋がります。
具体的には、バランスの取れた食事、適度な運動、十分な睡眠、禁煙、節酒などを心がけることが大切です。塩分の過剰摂取は高血圧のリスクを高め、心臓に負担をかけるため、減塩を意識した食事を心がけましょう。適度な運動は、血行を促進し、心臓の機能を維持するのに効果的です。ウォーキングやジョギング、水泳など、無理のない範囲で継続することが大切です。睡眠不足は自律神経のバランスを崩し、不整脈を誘発する可能性があるため、十分な睡眠時間を確保しましょう。
| 項目 | 具体的な改善策 |
| 食生活 | バランスの良い食事を心がける、1日6g未満の減塩を意識する、野菜や果物を積極的に摂る、暴飲暴食を避ける |
| 運動 | 週に3回以上、30分程度の有酸素運動を継続する、ウォーキングやジョギング、サイクリングなど無理のない範囲で行う |
| 睡眠 | 毎日同じ時間に寝起きする、寝る前にカフェインやアルコールを摂らない、リラックスできる環境を作る、7時間程度の睡眠時間を確保する |
| 禁煙 | 完全に禁煙する |
| 節酒 | 飲酒量を減らす、あるいは禁酒する |
心電図異常の再発防止策
心電図異常を一度経験した方は、再発を防ぐために、上記で述べた生活習慣の改善を継続することが重要です。規則正しい生活リズムを維持し、ストレスを溜め込まないように心がけましょう。趣味やリラックスできる活動を通して、ストレスを適切に管理することが大切です。
また、定期的な健康診断や医師の診察を受けることも重要です。心電図検査だけでなく、血圧測定や血液検査なども合わせて行うことで、心臓の状態を総合的に把握し、早期発見・早期治療に繋げることができます。
ご自身の心臓の状態を理解し、適切な治療と生活習慣の改善を継続することで、健康な状態を維持できる可能性は高まります。何か気になる症状があれば、すぐに医療機関を受診し、医師に相談しましょう。
まとめ
心電図異常と診断された場合、不安を感じるのも当然です。しかし、種類は様々で、必ずしも深刻な病気とは限りません。この記事では、短QT症候群や肥大型心筋症など、代表的な異常とその特徴、治療法について解説しました。
症状は、動悸や息切れ、めまい、胸痛など様々で、自覚症状がない場合もあります。検査方法は、安静時心電図、運動負荷心電図、24時間心電図、心臓超音波検査などがあり、状況に応じて適切な検査が選択されます。
治療法は、薬物療法、カテーテルアブレーション、ペースメーカーやICD植え込みなど、異常の種類や重症度によって異なります。日常生活では、バランスの良い食事、適度な運動、十分な睡眠、禁煙・節酒を心がけ、ストレスを溜め込まないよう注意しましょう。
心電図異常と診断された場合、または気になる症状がある場合は、決して自己判断せず、医療機関を受診し、専門医の診察を受けてください。早期発見・早期治療が、健康な生活を送る上で非常に大切です。医師と相談しながら、適切な治療と生活習慣の改善に取り組むことで、安心して日々を過ごせるようになりましょう。
参考文献
Bjerregaard P, Gussak I. Short QT syndrome. Annals of noninvasive electrocardiology 10, no. 4 (2005): 436-40.